父が死んだ。
ざまあみろ、と俺は思った。
彼がこの世界に置いていったのは、吹けば飛んでしまいそうな幾ばくかの遺産と、
二人目の妻と、その息子と、そして俺だけだった。
彼が存在していたことを明確に証明するものなど、何も残らなかった。
或いはそれが人の死と言うものだ。
父が再婚したのは去年の暮れで、結局それから半年もしないうちに脳卒中で倒れ、あっけなく死んだ。
彼がなぜ今更にして再婚しようなどと思ったのか、正確なところはよくわからないが、
たぶんに、彼女の10歳になる息子がいくらか関係していたのかもしれない。
でも彼は、結局目的をろくに達することなく果ててしまったわけだ。
だから、俺が代わりに頂くよ。
ざまあみろ、と俺はもう一度思う。
日曜の昼過ぎ、部屋の片づけをあらかた済ませたところで見計らったようにチャイムが鳴った。
心当たりのある人物は一人しかいなかった。
義理の弟、来月11歳の誕生日を迎える優斗だ。
「開いてるよ」
俺は玄関口に向かって、彼に聞こえるようにそう言った。
少しだけ間があって、やがてドアの開くガチャリという音が部屋に響いた。
そちらに目をやると、案の定、優斗が立っていた。
「来たよ」
薄ら笑いのような笑みを浮かべて、優斗はこっちを見ていた。
俺もそれを見て、微笑み返す。
なにも愛想笑いではない、本心から来る自然な笑みだ。
俺と優斗は歳が16も離れている。
息子と言っても違和感はないくらいの歳の差だった。
一人っ子でずっと育ってきた俺にとって、いきなり弟ができたと言われても、
そんな実感はすぐに沸くはずもない。
彼にとってもそれは似たようなもののようで、兄としてよりは父親のような頼り方をしていた。
こんなふうに、日曜日になると一人暮らしをしている俺の部屋まで時折やってきては、
暗くなるまで俺と遊んだ。
俺の下心など微塵も知る由無く。
「お母さん、元気か?」
「うん。たまにはこっちにも遊びに来てねってゆーといてって、お兄ちゃんに言っとった」
微妙な西の訛りが混じる喋り方、それと「お兄ちゃん」という呼び方。
人見知りの俺とは違って、誰にでも人なつこい笑顔ですり寄っていく優斗が少し羨ましいなと、
俺はいつも思う。
まだこんなに幼いのに俺の持っていないものをいくつも持っている優斗が、羨ましい、と。
俺はと言えば、まだろくに彼の名前を呼ぶことも出来ない。
「ご飯は食べたのか? サンドイッチくらいならすぐ作れるけど」
「ううん、そんなにお腹空いてないし、ええよ。それより、アレやらして」
アレ、というのは先週発売されたばかりのTVゲームのことだ。
一介のゲームジャンキーである俺のコレクションは、
ねだってもなかなか買ってもらえない彼のような少年にとっては絶好の羨望の対象だ。
でも、理由なんてどうだってよかった。
彼が俺を慕ってくれるなら。
まだ目新しい最新のハードのコントローラーを操り、彼はその仮想世界に熱中していく。
無防備に揺れる彼の身体を横で見ているだけで、俺は胸が熱くなった。
それを当然、彼は知らない。
その意味も、その感情も、彼は何も知らない。
これから俺が教えてやるんだ、と思う。
ゲームがひと段落したところで、彼は少し疲れたように俺のベッドに腰掛けて息を吐いた。
「学校、楽しいか?」
と俺は訊いてみた。
在り来たりな質問だ。
「うん。友達もできたよ」
「好きな子は?」
「えーっ、そんなんおらんよ」
照れたように顔を背ける。
いかにも、この年頃の少年らしい反応だ。
「お兄ちゃんは? 好きな人とか、結婚する人とかおらんの?」
「結婚はどうか、まだわからないけど、好きな人ならいるよ」
「誰?」
「すぐ近くにいる人」
「えー、同じマンションに住んでる人? 会社の人?」
彼は、何も知らない。
それがもどかしくも愛おしい。
彼はただ純粋で無垢で、媚びること、計算することを知らない。
俺の下心を、知らない。
「なあ、お前は、俺のこと好きか?」
と俺は訊いてみる。
「ん? うん、なに、急に」
「俺はお前のこと、好きだよ」
「うーん、僕も、お兄ちゃんのこと好き、かな」
「ありがとう。でもな、たぶん、お前の思ってる好きと、俺の好きはちょっと違う」
「じゃあ、どういうこと?」
身構えることもなく、彼は頭ひとつ分高いところにある俺の目をのぞき込んだ。
彼の心にあるのは好奇心だけだ。
それを可愛く思う俺と、少し意地悪い俺の部分とが重なって、俺を不思議と高揚させる。
純粋さを壊してしまいたい。
俺は背を屈めて、彼の唇を奪った。
抵抗するかと思ったが、彼はただ呆然とするだけで、身動きひとつしなかった。
すぐ近くにある彼から、少年の匂いがする。
その匂いが俺の中のスイッチを入れる。
ほんの数秒か、数分か、それはよくわからないが、しばらく後に唇を離すと、
やはり彼はどうしていいかわからないように身体を固めたままで、
ほんの少し赤らんだ顔を隠すように俯いた。
「びっくりした?」
と俺は言った。
「なに、急に」
彼の声はあからさまに小さく細くなっている。
「意味、わかるだろ?」
「でも、そんなの、ホモやん」
「ホモは嫌か?」
彼は何も言わなかった。
生理的な嫌悪があってもいいはずだったが、彼はそれさえ忘れ、静かに動転しているようだった。
でも、このまま流すのは少し卑怯かと思い、俺は彼の本心を探った。
「嫌ならもうしないよ。でも、嫌じゃないなら」
「わかんない」
と彼は俺の言葉を遮るように言った。
「もう一回、してもいい?」
彼は今度は何も言わなかった。
でもしばらくしてから、ためらいがちに顔を上げた。
俺はゆっくり顔を近付ける。
彼は逃げなかった。
彼の唇を吸い、舌を差し込む。
それを知らない彼は、ただ俺の肉を咥内に受け入れ、じっとしていた。
「怖いか?」
「わかんない」
わからなくなんてない。
怖いのだ。
俺はそれを、知っている。
「どうしてこんなことするの?」
と幼い頃の俺は、父に問いかけた。
「お前のことが好きだからだよ」
と父は言った。
俺を産ませて、早々に離婚した彼は、時折その大きな背中に寂しさを漂わせ、
それを俺に感じさせまいと必死に表情を繕っていた。
当然俺は、彼の感情も、その性癖も、まだ何も知らなかった。
「怖いか?」
と彼は訊いた。
「わかんない」
と俺は答えた。
わからなくなんてなかった、怖かったんだ。
でも俺は彼に抱かれるまま、その身体を委ね、やがて覚えた快楽に溺れていった。
そういった特殊な性癖は遺伝する、といつかどこかで聞いたことがある。
ならば俺も、やはり彼と同じものを内心に抱えていたのだろう。
いつか彼が俺を抱かなくなるまで、何度も快楽の夜はやってきた。
なんども汚された俺の下の穴は、今に至るまで父を求め続けている。
歪んでいるが故に、まっすぐな愛情。
その穴を埋める方法は、やはりひとつだけだ。
俺は優斗のペニスをじらすように丹念に舐めとった。
彼は自身の知らない未知の快楽に、どうすることもできずただ身を捩らせていた。
右腕は恥じるように自身の瞳を覆い、左手で拒否するように俺の頭を掴んでいた。
でもその力は戸惑うように弱々しく、何の意味も成さなかった。
「自分でしたことはあるか?」
俺がそう訊くと、彼はやはり顔を背け、口を硬く閉ざしていた。

「白いの、出たことは?」
「…あるよ」
「出そうになったら言えよ」
俺は枕元に準備していたローションで指を濡らし、
最初は撫でるようにそれを彼のアヌスにあてがい、
徐々に力を込めて中指を押し込んでいった。
「うっ」
彼は呻くようにそう漏らす。
でも俺は指を止めない。
「痛くないだろ?」
「気持ち悪い…、なんか、変」
「俺、お前の全部が欲しいよ」
と俺は言った。
それはかつて、俺が父に言われたことの繰り返しだった。
「俺お前のこと好きだよ。だから、全部欲しい。受け入れて欲しい。
お前はまだ知らないかもしれない、だからこれから俺が教えてやるよ。
俺のこと好きになってほしいから」
「いいよ」
と彼は相変わらず消え入りそうな細い声で答えた。
「お兄ちゃんなら、いいよ。でも、痛くしないで」
「大丈夫だよ」
大丈夫だよ、と俺は思う。
俺はなぜか、父にそう言われるのが好きだった。
耳元で聴く彼の低い声は俺を不思議に安心させ、触れ合う裸の胸の暖かさは俺をほっとさせた。
もし、彼の性癖だけでなく、そう言った特殊なものが俺にも受け継がれているのなら、
それを彼に分けてあげたい。
「大丈夫だよ」
と俺は、もう一度言った。
優斗は俺の腕の中で、何度も呟くように痛くしないで、と言った。
それがわずかに残った恐怖から来るものだと言うことも俺は知っている。
安心させるために、俺はゆっくりと慣らし、丁寧に愛撫した。
溺れてしまえ。
快楽に、愛情に。
そうすれば、痛みは消える。
消えた痛みの代わりに、終焉への恐怖がやってくる。
いつか必ず来るその時まで、俺の腕に縋り、その暖かさを貪ればいい。
「ううっううー!」
ゆっくりと、だが確実に俺のペニスが優斗の中にねじ込まれていく。
優斗は一度だけ、苦痛の混じった声をあげたが、
それ以上は口を閉ざし、ただ荒くなり始める呼吸の音だけを俺に聞かせていた。
「根本まで入ったよ」
「…」
「ひとつに繋がってる」
俺は少し無理な形で身体を折り畳み、挿入されたモノが抜けないように、彼の頬に口づけた。
彼も腰を持ち上げて、俺の上半身を受け入れた。
縋るように両腕を俺の首に回して、熱を求めている。
もう痛みはなさそうだった。
ゆっくりとしたピストン。
奥を突かれる度に彼は喉から声を漏らし、腕に込める力を強めた。
俺は右手で彼のペニスをしごき、絶え間ない快感を彼に与え続けた。
「でっ、出る…!」
そう言い終わるが早いか、彼は精液を自らの腹にまき散らした。
ドクドクとした脈が彼の中に入った俺のペニスにまで伝わった。
俺はそれをひとすくい、人差し指で拭って、ぺろりと舐めた。
やがて、彼の呼吸が落ち着いたところで再び腰の動きを再開させ、ほどなく俺自身も果てた。
優斗の腹の上で、二人の白濁液が混じり合った。
彼は半虚脱状態で俺の隣で息を潜めていた。
たまらなく煙草が吸いたかったが、それを我慢して、手近にあった飴を口に放りこんだ。
それは、父が俺によくくれたのと同じ飴だった。
俺は突然それを思い出して、そして彼の肉の暖かさを連鎖的に思い出した。
「ねぇ」
と優斗が言った。
「僕、今はよくわかんないけど、もっと知りたい」
「うん」
「もっといろんなこと教えて欲しい。そしたら、お兄ちゃんのこと好きになれると思う」
それはまだわからない。
今はただ幼さ故の無知を楽しんでいるだけかもしれないのだ。
かつての俺がそうだったように。
いつか、全てを知ったとき、この子は俺を恨むだろうか?
俺は彼に口づけ、口移しで飴を彼の口の中に移した。
「おいしい」
と彼は言った。



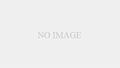
コメント